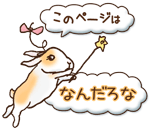かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
おもしろい木の実 ムクロジ
ムクロジの木
おもしろい木の実のなるムクロジの木について紹介します
初夏には爽やかな新緑が楽しめ、夏には大きな風通しの良い木陰を形成し、秋には美しい黄葉と有益な木の実が大量になり、冬には葉が落ちて陽だまりが楽しめるという事で、海外では庭にムクロジを植えるのが人気になっている所もあるそうです。

そんなムクロジの木が見せる四季折々の表情や樹木について紹介します。





ムクロジ(無患子)といえば、独特な形をした木の実や数珠や羽つきの羽根のおもりに使われた黒くて堅い種子を指すことが一般的なようです。