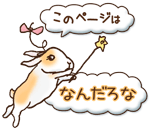かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
大仁田山周辺 季節の植物
ユキノシタ
大仁田山周辺の奥武蔵で見られた季節を彩る植物を紹介しています。

ユキノシタは5月から6月にかけて白く美しい可憐な花を多数咲かせます。
湿り気の多い岩場などの半日陰の環境で育ち、寒さにも強い丈夫な半常緑植物で、昔から民間薬として利用されてきた身近な植物です。

そんなユキノシタの花が咲くまでの過程や受粉に関する花の構造等について記載しています。

ユキノシタの名前の由来のひとつに白い花がちらちら降る雪のように見えるという牧野富太郎博士の説がありますが、時としてそのように感じる光景に出会うことがあります。

名前には諸説があり、緑色の葉に白斑があるのを表面に雪が積もった状態に見立てたとか、寒さに強く、雪の下でも葉が枯れずに残るから、とも言われています。


その他、花の下側の2枚の長い花弁を「雪の舌」に見立てたという説もあります。

ユキノシタ科 ユキノシタ属
学名:Saxifraga stolonifera
英名:Strawberry Geranium