かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
不思議で楽しい植物の世界
仏教三大聖樹
ムクロジ 番外編
縁起の良い仏教関連の木
仏教三大聖樹とはお釈迦様の生涯に関った3つの樹木の事で
無憂樹(ムユウジュ)
印度菩提樹 (インドボダイジュ)
沙羅双樹 (サラソウジュ)
を指します。
ムクロジとはまさに数珠つながりのページ

かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
仏教三大聖樹とはお釈迦様の生涯に関った3つの樹木の事で
無憂樹(ムユウジュ)
印度菩提樹 (インドボダイジュ)
沙羅双樹 (サラソウジュ)
を指します。
ムクロジとはまさに数珠つながりのページ

[マメ科サラカ属]
お釈迦様のお母様 マーヤー(摩耶) 婦人が無憂樹の花を愛で、一枝折ろうとした時にお釈迦様が生まれたと伝えられる木で、インドでは乙女の恋をかなえる木、出産や誕生、結婚等、女性にとっての幸福の木として愛好されているのだそうです。

英名でAsoka tree, Sorrowless treeと呼ばれるAsoka(アショカ)とは「憂い無し」という意味なんだそうで、これが名前の由来なんですね。

オレンジ色の花弁のように見えるのは萼です。

4月8日のお釈迦さまのお誕生日を祝う花祭りでは本来この美しい花を愛でていたということです。しかし耐寒性がないためか、日本では馴染みがないのが残念ですね。


葉は大きな羽状複葉で皮質。

熱帯地方では街路樹に利用され、夜に芳香を放つということです。

また、淡いピンクから黄緑色に変わるパステルカラーの若葉もしなやかできれいです。特にピンク色の葉は美しい花のように見えて魅力的。

お釈迦様は生まれた途端、七歩歩いて右手で天を指し、左手で地を指して天上天下唯我独尊(てんじょうてんげ・ゆいがどくそん)と話したという伝説は有名ですが、これは優越感に浸るおごった言葉ではなく、この世に唯一無二(オンリーワン)の存在として生まれた人の命の尊さを示しているのだそうです。

画像の出典:国立博物館所蔵品統合検索システム

[クワ科イチジク属]
お釈迦様が悟りを開いた所にあった印度菩提樹。天竺菩提樹とも呼ばれています。

お釈迦さま=ゴータマ・ブッダの別名であったボーディー(Bhodhi)から菩提樹という名前がつけられたそうです。

印度菩提樹はクワ科イチジク属の常緑性高木。寒さに弱いため、降霜のない地帯で育ち、大樹が自生する場所は地下水の存在を示す指標となるのだそうです。

葉はなめらかな革質でギザが無く、先端が尾状に長く尖っていて葉柄が長いのが目立った特徴です。


また、果実は鳥類に好まれ、種子は広範囲に散布されまが、数珠を作るのには小さすぎて不向きなので数珠作りには材を利用するのだとか。

[アオイ科シナノキ属]
日本の各地の仏教寺院に植栽されている菩提樹は、臨済宗の開祖である栄西が中国から持ち帰った中国原産のアオイ科シナノキ属の落葉樹だと伝えられています。


お釈迦様が悟りを開いた所にあったと言われるインドボダイジュは寒さに弱いため、葉の形が似ているこの木が代用されたそうで、植物学的には別種の樹木です。葉には鋭い鋸歯(ギザ)があります。


葉の裏は星状毛があるので白っぽく見えます。

花期は6月の上旬から中旬頃。

花序は細長いヘラ状の苞の途中から出た長い柄でぶら下がります。






秋にはたくさんの実がぶら下がり、落果し始めます。



お寺の方が親切にも実のついた枝を取ってくださいました。(感謝)




木質化した10mm✕9mmほどの実の中に5.5mm✕4mmくらいの小さな暗褐色の種子が1個入っています。

シューベルトの歌曲で知られている菩提樹は西洋菩提樹。
アオイ科シナノキ属の落葉樹です。

別名:リンデンバウム・セイヨウシナノキ
英名:コモン・ライム Common lime
独名:リンデンバウム Lindenbaum
仏名:ティユール Tilleul

葉にはギザがあります。

西洋でリンデンの名で親しまれているこの木の葉や花、樹皮は古くから民間薬として利用されてきたとか。

花期は6月の上旬から中旬頃。

日本の菩提樹と比べると、花はやや大きめで華やかです。

この花は優しく甘い芳香があって、リラックス効果のあるハーブとして利用されています。

たくさんのがぶら下がった実は秋に枯れ色となって落果します。



[フタバガキ科ショレア属]
お釈迦様が亡くなった所にあったという沙羅双樹は常緑高木で、沙羅樹(サラノキ・シャラノキ)とも呼ばれます。

沙羅双樹の双樹とはお釈迦様が亡くなった時にその四方にこの木が2本ずつ生えていたという伝説によるもので、沙羅の樹 の方が木の名前としては自然に思えます。

画像の出典:Wikimedia Commons
見渡す限り沙羅の樹林が続くクシナガラの二本並んだ沙羅の木の間で、頭を北にして右脇を下に、足を重ねて伏せて仏陀が涅槃に入ろうとする時、沙羅の樹の花が一斉に咲き誇り、仏陀を供養するかのごとく降り注ぎ、天から曼荼羅華が降り注いだと伝えられています。
[大パリニッバーナ経(大般涅槃経)]
耐寒性が弱いので、日本の気候では温室でないと育ちません。

春に白い花を咲かせ、ジャスミンのような香りを放つのだそうです。

画像の出典:Wikimedia Commons


[ツバキ科ナツツバキ属]
仏教三大聖樹の沙羅双樹は耐寒性が無いため、ナツツバキが日本各地の仏教寺院で沙羅双樹の代用として植えられてきました。

日本で、一般的に沙羅(シャラ)と呼ばれるナツツバキはツバキ科の木で仏教三大聖樹の沙羅双樹とは別種です。

6〜7月にかけて白くて清楚な花を多数咲かせます。


丸い蕾は宝玉のよう。




花は朝に咲き始め、夕方にポトリと花ごと落ちる一日花です。

やや大きめの花なので落ちた後にも存在感があります。
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす…
格調高い「平家物語」の冒頭に出てくることで有名な沙羅双樹の花は、次から次へとたくさん咲いては儚く終わるナツツバキの花の姿に無常観を重ね合わせたように思えます。



また、ナツツバキはモザイク模様の幹肌がとても美しい木なので庭木としても人気があります。



新緑も爽やかで綺麗です。

秋には美しく黄葉・紅葉し、その後落葉します。

果実は堅い木質の5裂する蒴果。

熟すと種子が姿を現します。

このページは「なんだろな」の中の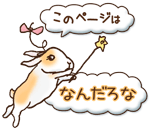
「不思議で楽しい植物の世界
仏教三大聖樹」