かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
時短発芽させた
ワタの成長
趣味の綿花栽培
時短発芽させたワタのその後の成長
魔法瓶を使って時短発芽させたワタですが、普通にちゃんと育つことができるのでしょうか?…ということでワタ栽培実験 第5弾・第6弾の発芽後に蕾をつけてからの成長記録と越冬後の成長記録を掲載します。
品種はアメリカ綿とアジア綿

結果は早期栽培が功を奏し、通常より早めにコットンボールが弾けて大成功となりました。


かわいいものが好きな方のための癒し系サイト
うさぎのぷうちゃんわーるど
魔法瓶を使って時短発芽させたワタですが、普通にちゃんと育つことができるのでしょうか?…ということでワタ栽培実験 第5弾・第6弾の発芽後に蕾をつけてからの成長記録と越冬後の成長記録を掲載します。
品種はアメリカ綿とアジア綿

結果は早期栽培が功を奏し、通常より早めにコットンボールが弾けて大成功となりました。

ワタ栽培第5弾 6月5日の様子。
5月になってから日照時間も増えて気温が高くなり、特に5月下旬からは最低気温も高めになり、大きな葉が増えて、蕾もつき始めました。

時短発芽実験開始から77日目と74日目と60日目。外気温が適温になったせいで4月6日に発芽実験開始してから60日目のワタの成長が速い結果となっています。
3月20日に時短発芽実験開始してから77日目のアメリカ綿。
魔法瓶発芽で幼根が出始めた時に土に植えつけ、4月21日、本葉が2枚の時に9号鉢に植えつけました。

▼一番大きな本葉は14cm位。

▼蕾がつき始めました。

3月23日に時短発芽実験開始してから74日目のアメリカ綿。
魔法瓶でもやしにしたものを土に植えつけ、4月24日、本葉が2枚の時に10号鉢に植えつけたもの。

▼一番大きな本葉は15cmを超え、順調に育っています。

▼脇芽も増えて大きくなり、密度が高いです。

▼蕾もつき始めました。

4月6日時短発芽実験開始してから60日目のアメリカ綿。
魔法瓶でもやしにしたものを水栽培して、側根が出てから4月10日に土に植えつけ、4月25日、本葉が出る前に9号位の角プランターに植えつけたもの。

▼一番大きな本葉は13cm位。

▼実験開始から74日目のものと比べても遜色ない程、のびのびを育っています。

▼小さな蕾もつき始めました。

3月20日に時短発芽実験開始してから77日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから60日目のアジア綿の様子。この2本はどちらも間引きし難く、10号鉢で2本育てています。

気温が高くなったせいか、背丈は違うものの、一番大きな本葉の大きさは同じくらいです。外気温が適温になった方が成長効率が良いようで、ほぼ同時期に蕾がつきました。

▼実験開始から77日目の蕾の様子。

▼60日目の蕾の様子。

ワタ栽培第5弾 6月12日の様子。
早めの種子まきにより、成長停滞期も終わり、この時期にしてはかなり大きく育っています。蕾の数も増えて順調に大きくなっています。
時短発芽実験開始から84日目と81日目と67日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから84日目のアメリカ綿。


3月23日に時短発芽実験開始してから81日目のアメリカ綿。


4月6日時短発芽実験開始してから67日目のアメリカ綿。


3月20日に時短発芽実験開始してから84日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから67日目のアジア綿の様子。


アジア綿の蕾を囲む副萼はやや緩めで少々大きくなると中が見えます。

副萼の中の様子です。

ワタ栽培第5弾 6月21日の様子。
蕾が徐々に大きくなり、数も増えています。葉の数も増えて丈も伸び、順調に成長しています。
時短発芽実験開始から93日目と90日目と76日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから93日目のアメリカ綿。



3月23日に時短発芽実験開始してから90日目のアメリカ綿。



ピラミッド状に3枚の副萼に囲まれたワタの蕾。

3枚の閉じられた副萼の中では蕾が少し大きくなっていました。

4月6日時短発芽実験開始してから76日目のアメリカ綿。


3月20日に時短発芽実験開始してから93日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから76日目のアジア綿の様子。



副萼の中では蕾が少し大きくなっていました。

ワタ栽培第5弾 6月29日の様子。
梅雨空が続き日照不足気味でしたが、久しぶりの陽射しのおかげか蕾も膨らみ、今年初めての開花が見られました。
元気良く発芽して育った苗は成長が速く、短期間で花を咲かせる結果となりました。発根時の選別は有用だと実感しました。
時短発芽実験開始から101日目と98日目と84日目。
雨のかからない環境で育てているせいか、ハダニが所々見られるようになりましたので霧吹きで葉が乾燥しないように水を散布して対処しています。
葉が赤褐色や白く色が抜けていたりしたら注意が必要です。
3月20日に時短発芽実験開始してから101日目のアメリカ綿。

蕾が膨らんできました。

蕾の中の様子。

これから2日後の7月1日、実験開始から103日目に一番花が開きました。
朝、蕾が開き始めます。

昼頃に完全に開花します。


夕方に花弁の縁がうっすらピンク色になって閉じ始めます。

翌朝にはきれいなピンク色になって花を閉じていました。

3月23日に時短発芽実験開始してから98日目のアメリカ綿。
発芽の時から元気が良かったこともあり、実験開始してから101日目のワタより速く初開花しました。

昨日、蕾から淡黄色のキャンドルのような花弁が姿を現しました。

早朝に花が咲き始めました。

クリーム色を帯びた白い花です。


午前中に花弁が開き始めました。

午後に花弁が大きく開きました。

花粉がたくさん出ています。

夕方になって花が閉じ始めました。

夜になって花が閉じました。
わずかにピンク色を帯びています。二番花の蕾が後ろに見えます。

翌朝にはきれいなピンク色になっていました。

これから2日後の7月1日、実験開始から100日目に三番花が開きました。
4月6日時短発芽実験開始してから84日目のアメリカ綿。


これから4日後の7月3日、実験開始から88日目に一番花が開きました。
今回の発芽実験でアメリカ綿では最短期間の開花です。

午前5時には花が開き始めました。

午前9時頃、花粉が出ています。


この日は曇天で午後3時頃になっても花が大きく開くことはありませんでした。

翌朝には花が淡いピンク色になっていました。

天候が悪かったせいか花は次の日の朝になってもきれいな状態で柱頭がピンク色になっていました。

午前中に花が落ちました。

花の中の様子です。
雌しべに花粉がついています。

落ちた花の跡を見ると、小さな実のようなものがついていました。
無事に受粉できたようです。

3月20日に時短発芽実験開始してから101日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから84日目のアジア綿の様子。前日には咲きそうな花の落花もあって残念でしたが、実験開始してから101日目のワタが初開花しました。


アメリカ綿と比べて小ぶりの花ですが、花弁は黄色が濃く、花の中央部が臙脂色でオレンジ色の葯と白っぽい柱頭が目立ち華やかです。

夕方には花が閉じ始めました。

アジア綿の方がアメリカ綿と比べて背丈の伸びるのが速く、前日に摘芯をしました。その後、アクシデントがあり、2本とも根元から倒れて、数枚の葉が落ちてダメージを受けてしまいました。残念でしたが、翌日には85日目のアジア綿の一番花も咲いてくれたので、とりあえす安心しました。

翌朝にはうっすらと淡いピンク色を帯びて花を閉じていました

思いがけず、速いペースで開花し、摘芯もしたこともあり、102日目のものと見分けがつかないほどになりました。
ワタ栽培第5弾 7月6日の様子。
日照不足が続いて心配でしたが、生育適温だったためか、次々と開花して実も大きくなり始めました。
時短発芽実験開始から108日目と105日目と91日目。
葉にクネクネと白い迷走したようなラインを描いて食害するエカキムシとも呼ばれるハモグリバエの幼虫の被害がありました。
幼虫は葉肉の白いラインの先端にいるので潰して退治しました。
3月20日に時短発芽実験開始してから108日目のアメリカ綿。

昨日、咲いた花がピンク色になって閉じています。

3月23日に時短発芽実験開始してから105日目のアメリカ綿。
次から次へと花を咲かせています。


受粉を終えてコットンボール(実)がつき始めました。

実の横には明日咲きそうな黄色の蕾が待機しています。

4月6日時短発芽実験開始してから105日目のアメリカ綿。

速いペースで花を咲かせています。

3月20日に時短発芽実験開始してから105日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから91日目のアジア綿の様子。


次々と花が咲いてコットンボール(実)もつき始めました。

ワタ栽培第5弾 7月13日の様子。
相変わらずの日照不足が続いて心配でしたが、花は咲き続けて実もそれなりに大きくなってきました。
時短発芽実験開始から115日目と112日目と98日目。
鉢の大きさに対して背丈も大きくなってきたので7月7日・11日に摘芯をしました。
鉢があまり大きくなくてもそれなりに育ちますが、やはり鉢が大きい方がずっと育ちが良いです。
また、最初に複数本植えつけてから間引きをした方が成長が良いというような結果となりました。
3月20日に時短発芽実験開始してから115日目のアメリカ綿。

4番・5番目の咲き終えたピンク色の花と少し大きくなった3個の実が混在しています。


主茎が木質化してきました。

3月23日に時短発芽実験開始してから112日目のアメリカ綿。
10番・11番目の花が咲いて現在一番多くの花を咲かせています。



ピンク色になった花の横では1番果が少し大きくなっています。

4月6日時短発芽実験開始してから98日目のアメリカ綿。


3番目の花が咲き終わり、翌日咲くであろう4番花のキャンドルが姿を現しました。

3月20日に時短発芽実験開始してから115日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから98日目のアジア綿の様子。

115日目のアジア綿は5番目の花が咲いて、98日目のアジア綿は6番目の花が咲いて花の数では追い越しました。

1鉢に2本は狭いのか、日照不足なのか、小さな蕾や実もポツリポツリと落ちています。

小さな蕾はたくさんついているので、どちらのものか判断に迷うようになりました。

115日目のアジア綿の1番果は2.5cm位になりました。

ワタ栽培第5弾 7月20日の様子。
長引く日照不足。開花は減って実がそれなりに大きくなってきましたが落果しないか心配です。
時短発芽実験開始から122日目と119日目と105日目。
元気よく成長していた時の摘芯は残念な気がしましたが、これほど日照不足が続いては蕾をつけたとしても無駄になってしまうところでした。摘芯をして良かったです。
いろいろな虫がやってきて、ちらほら被害が出ています。ワタが自己防衛のために備えているゴシポールは役にたっているのでしょうか?
3月20日に時短発芽実験開始してから122日目のアメリカ綿。

6番・7番目の咲き終えたピンク色の花と少し大きくなった5個の実が混在しています。


開花から18日目の1番果の大きさは約3.5cm。

3月23日に時短発芽実験開始してから119日目のアメリカ綿。

大小様々な11個の実と12番目の咲き終えたピンク色の花が混在中。

葉の裏側が見える方から見た方が実が確認しやすいです。

開花から22日目の1番果。
隣は開花から13日目の8番果。

開花から21日目の2番果。

それ以外の実も順調に膨らんできています。


4月6日時短発芽実験開始してから105日目のアメリカ綿。

4番目の花が咲き終わり、3つの実がついています。

開花から17日目の1番果。

3月20日に時短発芽実験開始してから122日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから105日目のアジア綿の様子。

122日目のアジア綿は7番目の花が咲いて実は4個です。

開花から21日目の1番果。
実の大きさは約3cm。

105日目のアジア綿は摘芯後も元気よく伸びてしまったので、再摘芯をしました。
8番目の花も咲きそうで、実は5個ついています。

開花から21日目の1番果。

日照不足とスペースが狭いせいか小さい蕾と実の落果が続いています。

6月28日にアクシデントで2本とも根元から倒れてしまったのも不良の原因かもしれません。
ワタ栽培第5弾 7月27日の様子。
思いがけず長引く日照不足。
実はそれなりに大きくなって存在感が出てきました。
時短発芽実験開始から129日目と126日目と112日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから129日目のアメリカ綿。

8番目の咲き終えたピンク色の花と大小合わせて8個の実が混在しています。


9番目の蕾も翌日咲きそうです。

3月23日に時短発芽実験開始してから126日目のアメリカ綿。

大小様々な12個の実と15・16番目に開いた花が混在中。悪天候が続いたせいか、25日に小さな実が1つ落ちてしまいました。

早朝にキャンドル状のクリーム色の蕾が開き始めました。

葯はまだ開いていないようです。

昨日咲いた花もきれいなピンク色になって閉じかかってます。
バランスが悪くて少し傾き始めたので仮の支柱を立てました。

実も順調に大きくなっています。

早朝に開き始めた花は夕方に閉じ始めます。曇天や雨の日は閉じるのが遅くなる傾向があります。

4月6日時短発芽実験開始してから112日目のアメリカ綿。

この鉢には元々3本の苗を植えつけていたため、間引き後に残った苗が角にあったため、バランスが偏り、傾きが大きくなってしまったので、仮の支柱を立てました。

昨日、5番目の花が開花しました。
朝にはピンク色になっていて、その他4つの実がついて、順調に育っています。

3月20日に時短発芽実験開始してから129日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから112日目のアジア綿の様子。
112日目のアジア綿は摘芯後に脇芽を伸ばし、122日目のアジア綿の上に覆いかぶさるように花を咲かせて実をつけています。

122日目のアジア綿は8番目の花が咲いて実は5個です。

112日目のアジア綿は11番目の花が咲きましたが、落果もあって実の数は7個です。
長期間、天候に恵まれないせいか、蕾や未熟果が落ちやすいようです。

10号鉢に2本は狭いらしく、葉が茂って重なり合う中央部には花芽ができません。

アジア綿を2本植える場合は横長のプランターの方が効率が良いのかもしれません。
ワタ栽培第5弾 8月中旬の様子。
長い梅雨があけ、ワタ栽培にとっておあつらえ向きの晴天続き。
強い陽射しのおかげで、元気良く、順調育っています。
アジア綿の実が早々に開絮!
丸くて白いかわいらしいわたが姿を現し始めました。
開絮(かいじょ)
ワタの実(コットンボール)が成熟後、乾いて裂開すること。ワタの実は蒴果で3〜5室に分かれ、種子は綿毛に覆われている。実が弾け、ふっくらとした白いワタが出てきたような印象がある。
乾燥によるハダニ対策が不可欠で、毎朝霧吹きで葉に水をかけ、鉢にもたっぷりの水やりをしています。
8月14日のアジア綿の様子です。

3月20日に時短発芽実験開始してから145日目の8月12日の早朝に、アジア綿が初開絮し始めました。

翌々朝の8月14日にはふっくらとしてきました。

同日の8月14日の早朝、4月6日に発芽実験開始してから129日目のアジア綿も初開絮していました。

続いて2番果も開絮し始めました。

アジア綿の実はアメリカ綿と比べて質量が少ないので開絮が速めです。
過去最速の開絮となりました。
ワタ栽培第5弾 8月23日の様子。
好天に恵まれたおかげで、アジア綿に続いて、アメリカ綿の実も開絮し始めました。
時短発芽実験開始から156日目と153日目と139日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから156日目のアメリカ綿。

ついに1番果が開絮。

15・16番目の花も咲き、まだまだ花が咲き続けそうな気配。

まだ8月、コットンボールと花と蕾が1枝にリズミカルに並ぶ様子に期待も膨らみます。
3月23日に時短発芽実験開始してから153日目のアメリカ綿。

こちらも1番果が早朝に開絮し始めました。

しばらく咲かなかった花も再び咲き始めました。今回で18・19番目の花となりました。

4月6日時短発芽実験開始してから139日目のアメリカ綿。

このアメリカ綿は現在、最も勢いがあり、8月21日、アメリカ綿で最初に開絮し始めました。

23日には2個めも開絮し始めました。発芽時期は前の2つと比べて遅いのに追い抜いてしまいました。

このアメリカ綿は摘芯後、枝をほぼシンメトリーに伸ばし、花も同時に咲かせ続けて2トップ状態です。

この日は他の枝の花も咲いたので4つも花を咲かせています。23番目の開花となりました。

3月20日に時短発芽実験開始してから156日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから139日目のアジア綿の様子。


この時期の弾けたコットンボールはすぐ乾燥して白いわたが落ちてしまいそうになるので、早々に収穫してしまいました。どちらも4個収穫し終えています。




毎日きれいな花を複数咲かせ続けているので今後も楽しみです。

ワタ栽培第5弾 8月26日の様子。
アメリカ綿の実が次々と弾けて綿花と花と実が共演して良い感じです。
時短発芽実験開始から159日目と156日目と142日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから159日目のアメリカ綿。
開絮し始めたものも含めると、4個の実が弾けました。

待望のふっくらコットンボールが姿を現しました。



23・24・25番目のクリーム色の花と昨日開花してピンク色になった花も混在して賑やかです。

3月23日に時短発芽実験開始してから156日目のアメリカ綿。

開絮し始めたものも含めると、5個の実が弾けました。
気温が高くて乾燥気味なので数日でふっくらとしてきてきました。

白いふっくらとしたコットンボールがなんとも可愛らしい。

22・23番目の花も咲きました。


枝先に並ぶ実と蕾が空也上人立像の唱える念仏の6体の阿弥陀仏のように見えてなりません。
4月6日時短発芽実験開始してから142日目のアメリカ綿。

気温が高くて乾燥気味なので弾けた2個の実は数日でふっかふか。


このアメリカ綿はここ数日花盛り。

この日、29〜33番まで5個の花を咲かせました。

ワタ栽培第5弾 9月14日の様子。
次々と弾けていたアメリカ綿の実も一段落ついて落ち着いてきました。猛烈な暑さも落ち着いて、新しい実が弾けるまで小休止のようです。
時短発芽実験開始から178日目と175日目と161日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから178日目のアメリカ綿。
これまでに10個の実が弾けました。現在6個の実を収穫して4個の白いワタが弾けています。

強烈な陽射しと乾燥が収まってから白いワタが開くのがゆっくりとしてきました。

42番と43番目の花が開花しましたが、花期も終わりそうです。

ふっくらと大きめのコットンボールが愛らしいです。

9月17日までに弾けて収穫し終えた10個のコットンボール。

3月23日に時短発芽実験開始してから175日目のアメリカ綿。

これまでに16個の実が弾けました。現在10個の実を収穫して6個の白いワタが弾けています。




昨日、夏休みの宿題を急いで仕上げるような勢いで44番と45番と46番目の花が開花していました。

花から弾けるまでのコットンボールが整然と並ぶ様子が楽しいです。


9月17日までに弾けて収穫し終えた16個のコットンボール。

4月6日時短発芽実験開始してから161日目のアメリカ綿。
これまでに5個の実が弾けました。

8月下旬に花盛りを迎え、9月3日に49番目の花を咲かせました。


その後は開花も開絮もありませんが、枝先の実が多くて枝がしなってきたので麻縄で誘引しました。


発芽からの日数は少ないのに開花の数は今期の中で一番多いです。が、落果も多いのが残念です。

9月17日までに弾けて収穫し終えた5個のコットンボール。
その後、ポツリポツリと開絮し続けて179日目の10月2日には12番まで実が弾けました。

10月4日の様子です。

天候もそれほど良くもなく、気温が低くなってきたせいか、ふかふかのコットンボールが枝先で長持ちしています。

7個の白いふっくらコットンボールが揃う様子が見れて嬉しいです。

10月13日、このコットンボールを7個収穫しました。

3月20日に時短発芽実験開始してから178日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから161日目のアジア綿の様子。

ワタ栽培第5弾 11月3日の様子。
9月下旬から朝晩の気温が下がり、10月中旬にかけて相変わらず陽射しが少なく、気温が低くなってきたせいか、少しずつ弾けたふかふかのコットンボールが長持ちしているので、長い間収穫せずに楽しむことができました。

栽培後期になってコットンボールはそれなりの数が弾けましたが、質や大きさを考慮すると、前期に弾けた物の方が全体的に良い結果に。
今季、早い時期に収穫できたことは有意義だったと実感しています。
また、気温の低い時は室内に入れてているので、ハダニにやられた箇所は痛んでいますが、緑色の葉が比較的長持ちしています。
時短発芽実験開始から228日目と225日目と211日目。
気温の低下とともにハダニが減り、ついにいなくなったと喜んだのもつかの間、夜間の室内避難の影響もあってかアブラムシが発生。初期段階だったので無農薬で駆除できました。
今季はワタノメイガ対策で夜間室内に入れていたことも、葉を長持ちさせるのに効果的だったと思われ、外に置きっ放しのものは数日でかなりの被害を受けました。害虫には苦労させられます。
3月20日に時短発芽実験開始してから228日目のアメリカ綿。

10月中旬から11〜19番までの実が弾けました。


早くに弾けていたコットンボールはふっくらからほわほわ状態。




いろいろな状態のコットンボールが混在している様子が楽しいです。


3月23日に時短発芽実験開始してから225日目のアメリカ綿。

10月下旬から17〜23番までの実が弾けました。このコットンボールは8月22日から26日に咲いていた花です。開花後、約60日で開絮。
17番目の実は開絮後15日の様子となります。

緑色の茂った葉の中に近い距離で実がなっています。

まだ弾けていない、青くて堅い実も数多く残っています。



たくさん実がついても大きくて良い実ばかりではありません。

小さかった19番花は実が小さく、開絮も時間がかかりました。

4月6日時短発芽実験開始してから211日目のアメリカ綿。

10月13日までにコットンボールを12個収穫後、10月19日〜11月3日までに13〜23番果の11個が続けて開絮しました。


コットンボールは弾けてから時間がたつとホワホワになってきます。






葉などに擦れると、コットンボールの繊維がほどけてきます。

花期終盤に枝先に次々と花を咲かせたものは実が少々小さめでいびつな傾向がありました。

3月20日に時短発芽実験開始してから228日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから211日目のアジア綿の様子。


3月20日に発芽実験したアジア綿はまだ堅い青い実が3個、4月6日に発芽実験をしたアジア綿は弾けたコットンボールが1つだけですが、どちらも枝先に小さな蕾を複数つけています。

気温が低下し、10月29日に咲いた花が1日で散らずに残っているように、これから花を咲かせたとしても実となることはなさそうです。
同じ鉢で栽培したため、枝が混雑してどちらかが判別しにくくなってしまいましたが、10月中旬ごろまで少しずつ開絮し続けました。


3月20日から発芽実験を開始したアジア綿は8〜15番、4月6日に発芽実験したアジア綿は7〜13番のコットンボールが穫れました。

今季、この10号鉢で育てた2本のアジア綿から合計28個のコットンボールが収穫できました。

ただ、結果の良し悪しは単純に個数だけでは判断できません。
初期に開絮したコットンボールの方が大きくて優良なものが多い傾向があるからです。

ワタ栽培第5弾 11月7日の様子。
11月上旬から朝晩の気温がかなり下がり、葉も落ちてきて成長が望めないので、アメリカ綿は実のついた枝を切ってドライフラワーにして開絮を待つことにしました。
時短発芽実験開始から232日目と229日目と215日目。
3月20日に時短発芽実験開始してから232日目のアメリカ綿。
コットンボールのついた枝を大胆にカット。根元から25cmほど残した土は来年のワタ栽培に使用する予定です。

未開絮から開絮しかかった実は5個残っていました。

11月29日にようやく最後の1つが開絮し始め、ドライフラワーが完成しました。

この9号鉢1本からコットンボール24個が収穫できて終了です。

3月23日に時短発芽実験開始してから229日目のアメリカ綿。
根元から30cmほど残して枝を大胆にカット。土は来年のワタ栽培に使用する予定です。

11個のコットンボールがついた枝をそのまま乾燥。

12月10日にようやく最後の1つが開絮し始め、今季の栽培実験が終了しました。

コットンボールはこの10号鉢1本から36個収穫できました。


4月6日時短発芽実験開始してから215日目のアメリカ綿。

11月12日に小さいですが、最後の1つが開絮し始め、今季の栽培実験が終了しました。

この角プランター1本からコットンボール26個が収穫できました。

3月20日に時短発芽実験開始してから232日目のアジア綿と4月6日に発芽実験開始してから215日目のアジア綿の様子。
蕾がたくさんついて、葉も比較的元気なので栽培続行しています。

時折、花を咲かせていますが、11月中旬を最後に完全に開くこともなく終わっています。

コットンボールはこの10号鉢2本から28個収穫できました。

その後、未開絮の実が2つ残っていたので栽培を継続したところ、1月下旬になってようやく弾けました。

しかし、わたは硬いままでほわほわするまでには時間がかかりそう。

寒波で葉に元気がなくなり、幾つかあった蕾もドライフラワーとなって咲かずに終わったので収穫を終えて枝を剪定しました。

ワタ栽培第5弾 越冬後4月16日の様子。暖冬のおかげで、暖房無しの部屋ですべて無事越冬して芽吹き始めました。


ワタを越冬させた理由は新規のワタの苗を植え付ける際に栽培中のワタの土を使うと生育が良くなる結果が出ていたからです。


アメリカ綿は5年目にして初めて冬越しに成功しましたが、新規栽培用に土を利用するため、抜いたワタの木は地植えしました。
※10号鉢のアメリカ綿は芽吹いていましたが、3月に他の植物の土へ転用したので終了しました。
アメリカ綿の越冬栽培実験は超時短発芽させたワタの成長で育てたワタで継続中。


アジア綿は昨年に引き続き、今年も冬越しに成功。
越冬をしたワタがコットンボールをつけるまでの様子はコチラ。
3月26日に魔法瓶発芽を開始。
魔法瓶発芽実験開始から3週間目の様子です。


遅霜や気温の低下の心配もなくなり4月25日に越冬ワタ栽培した土にアメリカ綿の苗を植えつけ。


アジア綿の苗は越冬アジア棉と同じ鉢にコラボで植えつけ。


2021年は気温が高めで天候も比較的安定していたので、今までの栽培で最も成長が速いです。5月下旬には蕾も姿を見せ始めました。



越冬ワタの土も良い状態だったのかもしれません。
越冬アジア棉とアジア綿の苗は葉が大きくてどちらも勢いがあって蕾もついて良い状態です。



葉のフチのレース模様の穴は小さなシャクトリムシによるもので、早期に気づいてセロテープで駆除。大きな被害にならなくて良かったです。
6月下旬には蕾も増えて、摘芯するほど大きくなりました。

6月26日にアメリカ綿の1番花、28日に2番花、30日に3番花が咲きました。




こちらの鉢は6月28日にアメリカ綿の1番花、6月29日に2番花が咲きました。


越冬アジア棉とアジア綿も勢いよく茂り、摘芯しました。蕾もたくさんついています。6月28日にどちらも1番花が咲きました。

越冬アジア棉は29日に2番花も咲きました。


梅雨明け後は夏らしい天気が続き、次々と花が咲いて7月下旬には実も大きくなってきました。

7月26日に10号鉢のアメリカ綿は12番花が咲きました。

11個ついた実もそれぞれ順調に大きくなっています。

こちらのアメリカ綿は7月26日に6番花が咲きました。



実の数は10号鉢と比べると少ないですが、順調に育っています。

7月27日に越冬アジア棉は11個、新規のアジア綿は5個の実をつけています。越冬アジア綿が元気よく育つので新規アジア綿は脇で遠慮がちに育っています。


実は目立ちませんが、順調に大きくなっています。

越冬アジア棉になっていた双子の実も大きくなってきました。

7月下旬から天候不順の日が続き、日照時間は少なめでしたが、8月中旬から下旬にかけてコットンボールが弾け始めました。

8月24日のアメリカ綿の様子。
10号鉢のアメリカ綿は8月20日に2個のコットンボールが初開絮し、翌日にもう1個が開絮しました。



花は8月3日に17番目が咲いたのが最後で、落果も数個ありました。

8月29日に6個目と7個目、31日に8個目が開絮し始めました。
こちらのアメリカ綿は8月22日に1個のコットンボールが初開絮し、翌日にもう1個が開絮しました。



7月下旬から8月中旬にかけて花を咲かせ続けて15個まで花を咲かせましたが、日照不足で落果が目立ちました。

8月28日に3個目、31日に4個めが開絮し始めました。
8月17日に越冬アジア棉は7個、新規のアジア綿は4個の実が弾け始めました。

初期に弾けたコットンボールは天候不良もあってあまり質がよくありませんでしたが、双子の実もちゃんとふかふかのわたが顔を出しました。


暑い時期の弾けたコットンボールは白いわたが落ちやすいので、8月22日に越冬アジア棉を9個、新規アジア綿は4個収穫しました。

天候が悪かったせいか副萼も枯れ色となって質は今ひとつですが、昨年と同じようなペースの開絮です。

花は少しずつ咲き続けています。
8月28日にふっくらとして落ちそうになったコットンボールを収穫。
越冬アジア棉は2個収穫したので、11個目となりました。今回は大きめで質の良い実です。

新規アジア綿は3個目の収穫です。

8月下旬から9月中旬からにかけて日照不足が続き、弾けた後にカビてしまったコットンボールもあり、早々に収穫。開絮し始めた時に収穫してしまえば良かったです。
昨年と比べハダニの発生は高温乾燥の日が少なかったせいかほとんど見られませんでした。

9月26日のアメリカ綿の様子。
これまでに11個のコットンボールが弾けました。

今シーズンは成熟期の日照不足と長雨のせいで9月に収穫した綿花は種子がカビているものもあり、あまり良い結果とはなりませんでした。
こちらのアメリカ綿も同様です。
早めに収穫したものは白くふっくらと綺麗な綿花となりました。

8月26日にまでに7個のコットンボールが弾けました。

アジア棉は実が小さいためか完熟が早めなのでカビは少なめだったのですが早めに収穫して良かったです。
9月中旬頃にワタノメイガの幼虫が発生。早期に駆除したのですが、実の副萼付近は見落としてしまったため、若干の被害がありました。

9月26日までに、越冬アジア棉は18個、新規のアジア綿は5個の実が弾けました。

元気に大きく育った越冬アジア棉の方が収穫は多かったです。

同じ鉢で育てたせいでルーキーは勢力争いに負けてしまったようです。
10月になって急激に気温が下がってきましたが、10月の下旬になっても少しずつ花が咲き続けています。

気温が低いせいで受粉ができないのか、開花時間が夏季と比べて長く、数日の間、花が楽しめます。

10月26日のアメリカ綿の様子。
少し黄葉し、葉が減っています。
9月30日の12個めを最後に、実は弾けていませんが、たくさんの蕾をつけています。

こちらのアメリカ綿も同様です。

10月26日の様子。意外にも10月の中旬から花盛りでした。実をつけるには遅すぎますね。

8個目のコットンボールがようやく弾け始めました。
アジア棉はその後もコットンボールが弾け、今季越冬アジア棉は23個の収穫となりました。

10月11日に最後の収穫を終えた後、越冬アジア棉とアジア綿、どちらも切り詰め、今季の終了としました。

残念ながらルーキーは収穫の少ないままの終了となってしまいました。

11月は陽の当たる日中以外は室内に入れて管理しています。11月下旬になって霜が降り始め、急激に気温が下がってきました。
生育には厳しい環境ですが、意外にも花が咲き続け、葉も色づいているものが増えてきましたが、まだ多くが残っています。

11月30日のアメリカ綿の様子。
少し黄葉し、葉が減っています。
実は未だに弾けていませんが、4個の花の咲いた形跡が残っています。


こちらのアメリカ綿も同様です。

11月30日の様子。花が1つ開花中で咲きそうな蕾が1つ、花の咲いた形跡が4個残っています。小さな実がそこそこついています。


3月になってようやくアメリカ綿の残っていた実の開絮が始まりましたが、コットンボールの中は小さくてフワフワ感の少ないわたでした。

割と大きめの実で越冬したので期待していたのですが、やはり、春から夏に順調に育ったコットンボールの方が結果が良いようです。

このページは「なんだろな」の中の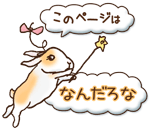
「時短発芽させたワタの成長」